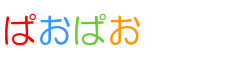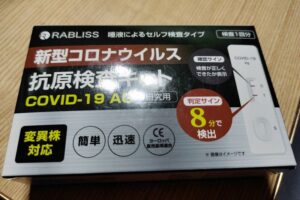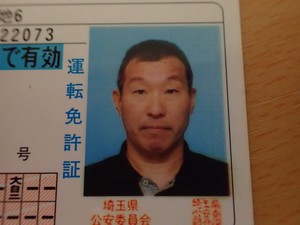車椅子のタイヤ交換とパンク修理を行ったのでちょっとレポートする。
うちのばーちゃんの車椅子なのだが・・・タイヤも随分と古くなっていた。じーちゃんが先日より空気を入れても、すぐに抜けてしまうとのこと。
というわけで、車椅子のパンク修理をすることになった。
この記事に書いてあるコト
車椅子のパンク修理は自転車屋さんでは厳しい

これがウチの車椅子だが、普通のママチャリのようにパンク修理をするのは厳しい。
なぜなら、ホイール外側についている車椅子を自分で手で漕ぐ部分(ハンドリム)が外側にあることにより・・・まずタイヤレバーが入らない。ということはタイヤが外側には外しづらいということがあげられる。
また内側にタイヤを外してチューブを出すという手があるが、これがまた非常にやりにくいことが予想される。
タイヤ交換などはお手上げだろう。
ちなみにハンドリムはタイヤが入ったままでは外すことができない構造だった。ボルト緩めてはずせれば一番いいのだが、スリットは入っていなかったので、全バラシをしないとハンドリムは外せない。
この状態でハンドリムが簡単に取り外せる構造であれば、非常に簡単にパンク修理もタイヤ交換もできるであろう。
なので、車椅子のパンク修理が簡単にできるかのポイントは、このハンドリムが簡単に外れるかどうかにかかっている。
車椅子のパンク修理は思った以上に難しい。今回は車椅子からホイールを外したパンク修理の方法、ホイールを付けたままタイヤレバーを使ったパンク修理の方法、さらにタイヤ交換の方法などを順番に解説をしていきたいと思う。
ホイールを本体フレームより外してタイヤ交換
まずは車椅子本体よりホイールを外してタイヤ交換をしてみよう。
チェックすることはホイールが車椅子本体フレームより外すことができるかを確認しよう。

幸いウチの車椅子はナット1つでフレームに固定されているタイプで、ここを緩めれば簡単にホイールを本体から外すことができた。

ホイールは無事に外れた。
パンクをチェックしてみると、普通のパンクではなくバルブの根本よりエアが漏れていて、チューブ自体がダメになっていた。はー・・・
タイヤも外すときにボロボロとカスが出てくるほど劣化していて、ゴムのしなやかさもほぼない。
仕方ないので、新品タイヤと新品チューブを発注。
車椅子のタイヤは自転車用タイヤでOK

お正月からアマゾンさん配達ありがとうございます。

うちの車椅子のタイヤサイズは22X1 3/8インチだった。チューブもそのサイズを新品1本購入。
大晦日に頼んでお正月の午前中に来た・・・
車椅子のタイヤ交換

タイヤは本当に普通のママチャリタイヤ。
たぶん普通の車椅子であれば、この22×1 3/8 WOタイヤだろう。ちなみに標準空気圧は300kPaとなっている。ロードバイクに比べるとめっちゃ低いな・・・空気圧。

車椅子のタイヤ交換もパンク修理もホイールさえ外れていれば、本当に簡単。
普通のママチャリと同様の感覚でできるだろう。
のんびりやっても30分程度で2本のタイヤ交換が完了をした。

新品タイヤに入れ替わった車椅子のホイール。

両方のホイールを組み付けて、車椅子のパンク修理、タイヤ交換無事完了。
車椅子のホイールを外さないでパンク修理する方法
車椅子のパンク修理をホイールを外さずやってみよう。車椅子はめったにパンクをしない。なぜなら自転車やバイクみたいに動力がないため、タイヤ自体に負荷がかからない。
さらに歩く速度のため、荷重も非常に少ないので路面からの影響があまりないことによる。
それでもタイヤの空気圧が少なかったり、段差でタイヤに衝撃を与えたり、チューブやタイヤの劣化などによりパンクが発生する場合もある。
自転車のパンク修理などをしたことがある人などは、以下の記事にある車椅子からホイールを外さないで、パンク修理する方法が参考になるだろう。
ホイールを外す工具がない方やパンク修理をやったことがある、パンク修理だけをするのであれば、以下の車椅子からホイールを外さないでチューブを取り出す方法が良いだろう。
車椅子を自転車屋さんに持ち込むのも非常に不便だ。ぜひここは車椅子のタイヤ修理、パンク修理の方法をチェックしておこう。
ホイールを外してパンク修理をする手順
車椅子の形状にもよるがホイールにハンドリム(ホイールを手で回すリング状のもの)が存在する場合、パンク修理が非常にやりにくい。
ホイールにハンドリムがついているタイプの車椅子の場合、2種類のパンク修理方法がある。
一つは以下に書いてあるホイールを外す方法だ。時間もかかりけっこう面倒な方法だが、自転車のパンク修理に慣れていない人の場合、車椅子にホイールを付けたまま修理をするとチューブに傷をつけたり、巻き込んだりして、使い物にならなくなってしまうかもしれない。
本体からホイールを外せば、タイヤを外すこともチューブを取り付けることも非常にやりやすい。またタイヤ交換やリムテープを張り替える場合なども、とてもやりやすいと考えます。
タイヤ片側をホイールより外しパンク修理
ママチャリのパンク修理をしたことがある方や、ホイールを外す工具などを持っていない場合などは、この車椅子からホイールを外さないで、パンク修理をする方法をおすすめする。
基本的にホイールにハンドリムがなければ、普通の自転車のパンク修理と同様に外側のタイヤを外し、チューブを取り出してパンク修理をすればいい。
しかし、ハンドリムが存在する場合、外側のタイヤを外すことはできない。ハンドリムがあるためにタイヤレバーを使うことができないからだ。
そのため、ハンドリムがある車椅子の場合、内側のタイヤを外し、内側にチューブを取り出して修理をすることになる。

内側のタイヤに1本目の(赤い)タイヤレバーを入れる。タイヤがリムから起きたら、2本めのタイヤレバーを入れる。

タイヤレバーを2本入れればタイヤは外れるだろう。あとはぐるっと一周タイヤをリムより外す。

内側に外れたタイヤよりチューブを取り出す。

チューブが外れたらバルブの部分を取り外す。

以上の方法でタイヤからチューブが外れる。
この状態でパンク修理をしても良い。またやりにくければ一旦チューブを車椅子本体より外してからパンク修理をしてもよいだろう。
修理したチューブをホイールに戻す

修理を完了したチューブは一旦ホイール内側に戻す。その後バルブの部分をホイールに挿入してから、チューブをもとに戻す。
チューブがもとに戻ったらタイヤを手で入れていく。バルブの部分から入れていくとよいだろう。
一番最後のタイヤのビードをホイールに入れるのが一番大変。入れる部分の逆側のビードをホイールリムの内側にできるだけ落として作業をするとタイヤレバー1本でタイヤを入れることができる。
タイヤレバーはできるだけ最後に1回だけ使うようにするとよい。全周タイヤレバーを使って入れると、タイヤとリムにチューブを噛み込んでチューブが傷つき、またパンクをしてしまう。

タイヤバルブにエアバルブを入れてからエアを入れる。
ほとんどの車椅子ホイールのバルブは英式バルブと思う。この際なので英式バルブの「虫ゴム」もチェックをしておこう。1年以上チェックをしていないと虫ゴムが劣化して、ここからもエアが漏れる。

以上で車椅子からホイールを外さないでパンク修理をする方法だ。
まとめ
自転車であれば、パンクしても、修理は次でいいや・・・あとに回すこともできるだろう。しかし、車椅子はそうは行かない。なんといっても、車椅子は日常的に利用し、また使うものであり、生活に必要なものだからだ。
車椅子のトラブルはそんなに無い。しかしあるとすればパンク修理やタイヤ交換となるだろう。動力がないので劣化やパンクなどはほとんど皆無の車椅子。
だからこそ、余裕のあるときにでも車椅子のタイヤチェックやパンク修理の方法を確認しておくとよいだろう。
そして車椅子のタイヤ交換は、ホイールが外れれば非常に簡単にできる。また外側のハンドリムが無いタイプの車椅子やハンドリムが外れれば、もっと簡単にパンク修理ができる。
しかし、ホイールが外れない場合、ハンドリムが外れない場合・・・かなり厳しいだろう。
車椅子のタイヤなんて、ほとんど交換する人はいないし、パンクするほどの走りもしないだろう。しかし、経年劣化や空気が入っていないタイヤで運用をすると、自転車並みにパンクはある。
以上よりもし車椅子を使っている場合、今後のことも考え、ぜひ車椅子のパンク修理、タイヤ交換はトライしておこう。
その場合、自身の車椅子のタイヤサイズを把握しておくといいぞ。ちなみにタイヤ外すと、だいたいリムテープもダメの場合が多いから、揃えておこう。ウチのもダメだったよ。